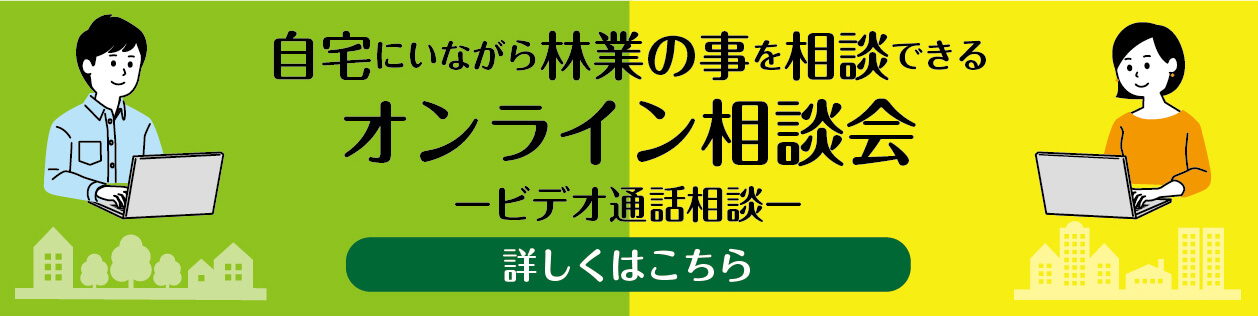「時代が来るから覚えとけ」親方から引き継いだ技術を次の世代へ
和歌山県の東南端、熊野川流域に位置する熊野川町。
世界遺産「熊野古道」はいにしえから、祈りと修行の場として多くの人々が訪れてきました。川の参詣道である「熊野川舟下り」は、現代でも大切に受け継がれています。この地で林業に従事し、21年目の鳥羽山誠一さんにお話を伺いました。
「好きに生きろ」父からの言葉で林業の道へ
「元々林業をしたいとかは全然なかったんです。和歌山市の実家で寿司屋の手伝いをしながら、大工をしていました。中学生の頃から「田舎で暮らしたい」という思いがありましてね。父から「年取ってから田舎に行くんやったら、もう若いうちから行け。田舎も年寄りなんかいらんねん、若い人に来てほしいんやから。跡取りなんかいらん。好きに生きろ」と言ってもらったことがきっかけです。
27歳のときに古座川町で開催された田舎暮らし体験に参加。そこで緑の雇用(林業の新規就業者支援事業)を紹介してもらい、那智勝浦町森林組合に入りました。新宮市の林業の会社に就職した後、独立、自営の経験も経て、現在は熊野川町森林組合で働いています」
若い子が吸収してくれることが喜び
鳥羽山さんの専門は「架線集材」。
ワイヤーロープを張り、伐採した木材を吊るしてロープウェイのように集積場まで運びます。急峻な山の上でも行え、車両道を作らないので山を痛めることなく、永続的な林業が可能となります。架線を設置するには、搬送経路の見極めや支柱となる樹木の選定など、高度な技術と経験を要します。そのため林業架線作業主任者という国家資格が必要です。
「僕が架線集材を習い始めた頃、若い人は本当にいなかったんですよ。その中でもうちの親方は『もう一回架線の時代が来るから覚えとけ。将来的に絶対に必要な技術やから』と言われました。親方に引っ付いてそこら辺のやつには負けまいと努力していましたね。それが今、親方が言っていたことがよくわかるんです。今やっぱり架線の時代に入ってきている。この技術がないと和歌山県の木材は利用できないところがたくさん出てきていると思います。それを覚えておいてよかったなと。
今では農林大学校や労確支援センターから講師に呼んでもらえることもあり、大変光栄やと思ってます。職場に若い子が一人入ってきてるんですけど、あいつがどんどん吸収してくれてるのを見ると、そこらが喜びですよね」

林業はなくなりはしない仕事
最近は林業の現場でも、デジタル技術が活用されています。鳥羽山さんも、親方から教わった技を引き継ぎながら、最新の技術も積極的に取り入れています。
「20年前に架線集材を習い始めた頃は、架線鉄砲といって、バズーカみたいなもので火薬でバーンってバインダーひもを飛ばしていました。今はドローンを使用しています。ドローンの場合、狙ったところにちゃんと行ってくれるので、大変楽ですね。
その反面、デジタル技術が入り込まない部分は、結局体力がいります。林業はなくなりはしない仕事やと思うんすよね。そういう意味では、先が明るいんかなと思います」

危険と隣り合わせの仕事であるからこそ、日々気を付けていることについて伺いました。
「一歩止まるというか、慌てないことを心がけてますね。あと疲れすぎない。疲れるとやっぱり判断能力って下がるじゃないすか。だから疲れてきたなと思うと、一呼吸おく。ちょっと休んでみたりとかはよくします。
これからは、穏やかに暮らしたいですね。田舎で暮らすのは意外と忙しいんですよ。いろんな地区の役だとか、そんなので日常もすごい忙しくて。ゆっくりやりたいことをやりたいですね」

中学生の頃から憧れていた田舎暮らしが「忙しい」と笑って話してくださる姿が印象的でした。最先端の技術を取り入れながら、長年培った技術を次の世代に伝えている鳥羽山さん。世代を超えて引き継がれている技術が、和歌山県の林業を、そして自然環境を守ってくださっているのだと感じました。